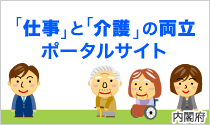在宅の看取りとは、病気をわずらった方をご自宅で介護し、親しい家族と一緒に最期を見届ける方法のことです。介護を受けているご本人の希望を叶えられるよう、今回は在宅で看取りをするための心構えと在宅看取りを行うタイミングをご紹介します。
在宅で看取りをするための準備
家族や親族との理解を得る(家族が目指すゴールを考える)
在宅看取りを行う際、最も大切なのは、ご本人と家族全員が、自宅での最期について理解をすることです。在宅での介護方法や医療をはじめ、今後起こり得る病状などを把握しなければなりません。もしご本人が自宅に帰ることを希望していても、在宅看取りを不安だと感じる家族がいるなら、その不安を担当医や看護師へ正直に伝えましょう。
ご本人の意思を尊重することも大事ですが、実際介護にあたるのは家族です。在宅での看取りにおいて、家族や親族全員の同意は必ず得てください。
家族ができること・できないことを把握する
在宅看取りを行ううえで陥りがちな考えは「介護すれば治る」ということです。病気や入院の場合は「治す」ことをゴールとして定めますが、終末期で介護をしても治ることはありません。家族は治すことに意識を向けるのではなく、「日々楽しく、そして安らかに過ごせる生活を支援すること」をゴールとして定めましょう。当人が痛みを抱えている場合は、体調の変化をいち早く察し、医療者に適切に伝えてください。ご本人の気持ちに傾け、そばに寄り添うことが大きな支えとなります。
ただし、家族の支えだけでは十分な力になれないこともあります。ご本人が感じる寂しさや心細さをすべて埋めるのも難しいものです。「死んだらどうなる?」と尋ねられる場合もあるようですが、その場合に自身の考えを押し付けては、当人を逆に苦しめてしまうかもしれません。家族にできることは、あくまで医療従事者や介護者の橋渡しと、ご本人のそばにいて接することのみです。家族ができる範囲で支えてあげましょう。
かかりつけ医とケアマネージャーを決める
在宅介護や看取りを行う場合、かかりつけ医とケアマネージャーを決める必要があります。かかりつけ医を探すポイントは、夜間や休日含め24時間診てくれる・往診を行なっているかです。すでにかかりつけ医がいる場合は、その方が対応可能か確認をしてください。対応ができない場合、もしくは見つからない時は、市町村の在宅医療相談窓口や地域包括支援センターで相談すると紹介してもらえます。
ケアマネージャーとは、訪問介護や看取りについてアドバイスを提供する人物です。できるだけ在宅での看取り経験のある方にお願いしましょう。ケアマネージャーもかかりつけ医と同様、同場所で紹介してもらえます。
要介護認定の再審査を受ける
支援の区分には「要支援」と「要介護」があります。要支援と要介護では、介護保険サービスの内容が異なるだけでなく、介護保険で毎月支給される保険の限度額に違いが出てきます。介護認定のやり直しを希望する場合は、介護認定の再申請(区分変更申請)を行ってください。この区分変更申請は、認定後に体調が悪化した場合に申請できます。もしくは認知症の方が、普段の状態よりも認定調査時のほうが体調が良かったことで、軽度と認定された場合に該当します。
要支援から要介護認定の区分変更になった場合は、新規として認定されることを把握しておきましょう。要介護認定の区分変更を希望する際は、その旨を必ず担当のケアマネージャーに伝えてください。了承を得たうえで、手続きを行う必要があります。
看取り体制を整える
在宅介護・看取り体制を整えるのも大切な準備の一つです。どのような療養生活を送りたいかご本人の希望を確認し、必要な看取り体制を整えます。訪問ヘルパーや訪問介護士をはじめ、薬剤師・歯科医師・管理栄養士なども一緒に探しておくと、いざという時でも慌てずに済みます。
とりわけ訪問介護は、在宅で看取るために必要不可欠なサービスです。食事をはじめ、入浴・排せつの介助や、かかりつけ医の指示にもとづく医療処置、症状の観察や痛みのコントロールなどのターミナルケアなどを行ってくれます。また、認知症看護の方法や服薬指導、看取り体制についての相談も可能。介護されるご本人はもちろん、家族のサポートもしてくれる存在です。訪問介護を希望する場合は、その旨をケアマネージャーに伝えましょう。
急変する可能性を念頭に置く
在宅で看取りをする場合、最期の時間は必ず訪れます。そのため、家族にも覚悟が必要です。夜中に起きて様子を確認しなければなりません。昼間は元気でも、夜になって容体が急変する可能性もあるでしょう。いつ何が起こるか分からないぶん、大変なことや辛い瞬間もたくさん訪れます。何が起きても冷静に判断できるよう、急変する可能性がある旨を念頭に置いてください。急変した際は、かかりつけ医やケアマネージャーにすぐ連絡できるよう事前に準備をしておくと、幾分か冷静に対処できます。
亡くなる前に起こる変化を把握しておく
死亡直前になると、さまざまな変化が訪れます。急に容態が変化するとパニックを起こす可能性もあるので、死亡前に起こり得る状態についてあらかじめ確認しておきましょう。
-
- 血圧が低くなり、脈拍が少しずつ弱まる
- 声をかけても反応が次第に薄くなる
- 手足が冷たくなる
- 顔の血色が悪くなり、青紫色に変わる
- 呼吸をする際に、ゴロゴロといった音が聞こえる
このような反応が見られた場合は、すぐに医師へ相談をしてください。ご本人のそばに寄り添い、温かいお声がけをすることが励みとなります。
亡くなった後の流れを確認しておく
家族で大切な方を見送った後は、医師が死亡確認を行い、死亡診断書を作成します。医師が死に際に間に合わない可能性もあるので、医師がその場にいなかった場合は死亡時刻をメモしておきましょう。
家族とのお別れが終わった後は、訪問看護師もしくは葬儀社が、亡くなった方のお身体を綺麗にし、メイクを施します。
在宅介護に切り替える時期
在宅に切り替えるタイミングは、ご本人の希望をはじめ、家族の受け入れ体制などを考慮したうえで決める必要があります。
現在家族が施設に入居している場合は、担当医に身体の変化について確認・相談し、どの段階で自宅に戻るべきか判断してください。
年齢が高い方を看取るタイミングは、食事ができなくなった時期とされています。人は死期が近づくと、食欲が衰えはじめ、食べ物や飲み物を必要としなくなるからです。家族もそのことは頭で分かっているものですが、実際はなかなか受け入れにくいものです。「少しでも食べて欲しい」と、ご本人に食事を与えたくなるでしょう。
それを考えると、本人が食べる意思がある状態・食欲がある時期に自宅へ戻ったほうが良いかもしれません。家族の判断のみで決めるのではなく、担当医や看護師、ケアマネージャーと話し合ったうえで、在宅介護に切り替える時期を判断しましょう。
ご本人が元気なうちに、お金関連や亡くなった後の話をするべき
できることならご本人が元気なうちに、お金関連の話をしておきましょう。本人の意識が昏睡した状態で、口座の種類や暗証番号、延命治療の有無などを確認できません。医師から延命治療の有無を委ねられた場合、本人の希望か分からないなかで、家族が判断するのはとても難しいものです。
「最期は自宅で過ごしたい」というご本人の希望はもちろん、葬儀やお墓についても話をしておくと、遺族は希望に沿った形でお見送りができます。*葬儀形式で、親族から「なぜこの形式にしたの?」と尋ねられることもあるでしょう。そんなとき、故人の遺志と返答できるのは、残された遺族によって大きな助けになります。悔いのない人生をまっとうできるよう、冷静に話せるうちに決めておきましょう。
*葬儀形式……日本には現在「一般葬」「家族葬」「社葬」「お別れの会」など様々な形式があります。