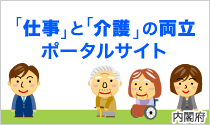正しい介助知識
体の不自由な人にたいして手助けをしたくても、正しい知識がなければ適切なサポートはできません。
例えば、杖をついて横断歩道を歩いているお年寄りを見かけた際の手助けは、杖側の手をとるのではなく、反対側の手をとる方がお年寄りの歩行の妨げにならずに手助けをすることができます。
サービス介助士とは、正しい介助の知識や技術を持ち高齢者や体の不自由な方のサポートをする人を指します。
サービス介助士は、おもてなしの心と的確な介助の技術を習得し、様々な場面で活躍をみせている、高齢化社会で非常に求められている存在です。
バリヤフリー化が広まっている今日の社会でも、体の不自由な方々にとっては一人での外出は困難なことも多くあります。
駅や空港、銀行や飲食店、デパートや宿泊施設や学校でサービス介助士のサポートは求められています。
サービス介助士の資格
サービス介助士は民間の資格となります。
受験資格もなくだれでも試験を受けることができるので、福祉係の資格の中でも受けやすい資格として人気です。
サービス介助士には4級~準2級、2級とあり、4級と3級は10代を対象とした体の不自由な人への理解を目的としています。
資格に1級は無く、実際に介助として活動できるのは実技試験もある2級取得者のみです。
しかし準2級から、2級と同じ介助の知識だけは勉強することができ、試験は実技もなく自宅での検定試験を受けることができます。
その内容は点字や手話、車いすの取り扱い方など、日常生活の中で困っている体の不自由な人への配慮に役立つ内容です。
資格を発行しているのはNPO法人日本ケアフィットサービス協会で、2級取得者数は現在で10万人を超えている資格となります。
サービス介助士の勉強を通して
サービス介助士がいる証としてその認定マークが貼られている企業や飲食店があり、社会福祉に取り組んでいることへの大きなアピールにもなります。
そして認定マークの持つ意味は、体の不自由な方でも安心してその施設が利用していただけることであり、ホスピタリティを持つ心の証です。
道にスロープがただあるだけではなく、介助への正しい理解を人々がすることによって、初めてバリアフリーが実現できると言えます。
専門学校などの教育機関でもサービス介助士の講座を取りいれるところもあり、その必要性は高いものと認識されています。
準2級までは通信教育での受験も簡単にできるので、サービス介助士の勉強を通して正しいおもてなしの心を学ぶ人は多いです。
入浴や食事、排泄といった介護の部分以外を除いた勉強ですが、その内容はボリュームのあるものなので、2級取得後の介助の技術は確かなものになります。
将来的に介護の仕事に就きたいと考えている人は、まず2級を目指して勉強してみることをおすすめします。