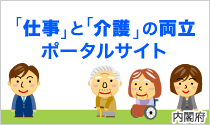女性のみの仕事
助産師とは妊娠中の母親の医学的な観察・指導・ケアを行い、新生児の観察・沐浴など、妊娠から出産、育児まで母子の健康を守る活動を行い、分娩時には、医師の指示を必要とせず、自らの判断でへその緒を切り、浣腸を施し、その他、助産師の業務に付随した行為など、助産および助産業務をします。
昭和世代のかたには、助産師という名称より産婆さんという呼ばれ方のほうが分かってもらえるはずです。
助産師は上記に示した仕事を行いますので、専門知識が必要なのは当然のこととして、国家試験に合格する必要があります。
その仕事の性格上受験資格もあり、看護師の資格もしくは看護師国家試験の受験資格を持つ者が、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の養成校(大学や短期大学、専門学校など)を卒業すると受験資格を得られます。
出産を行うには産婦人科に通院するだけではなく、助産師の手によって行われるケースがありますので、試験そのものが厳しいのは仕方のないことだといえるでしょう。
また助産師の試験を受けられるのは、女性のみとなっています。
産婦人科の医師は、男性も存在していますが、助産師は女性のみですので、この点も特徴の一つになっています。
就職として助産師を考えると、病院・診療所の産婦人科や地域の保健所、母子保健センターなどがあります。
また経験を積んだ助産師が独立して助産所を開業するケースもあり、就職に困ることはありません。
助産師の仕事
昭和初期以前は一般的には出産は産婆さんが行いました。
産婦人科で出産を行うのが一般化したのは、昭和中期以降になり助産師の仕事は減少しました。
ですが平成になり、家族構成などが再び変わると再び助産師の仕事は脚光を浴びています。
産婦人科はその性質上、往診を行うということはほとんどありません。
ですが助産師は妊婦の自宅を訪れてケアや指導をしたり、地域に出て母子相談や子育てセミナーを行います。
核家族化が進み、身近に相談をすることできない現代人にとっては必要のある仕事だといえるでしょう。
次に助産師はすべて女性であるという点が上げられます。
産婦人科の患者はすべて女性です。
しかし医師はすべてが女性とは限りません。
ですが助産師はすべて女性であり、女性が女性にみてもらうというだけでも安心感があります。
特に初産の女性にとっては、心強い味方と感じることができます。
また出産に限定したことだけではなく、性教育、不妊相談、家族計画、更年期への支援といった思春期~老年期までの、女性に関わる職業でもあるため、女性にとっては強い味方であり、やりがいのある仕事だともいえます。
ただし出産というものは、生命がかかった大切なもので、時にはさまざまなアクシデントがあります。
瞬間的な判断力や決断力は当然として、流産や死産という事態に立ち会うこともありますので、精神的な強さが必要です。