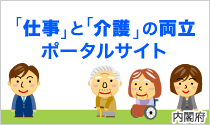医療事務従事者
医療保険士は、医療保険や医療事務の知識や実務能力を身につけている医療事務の認定資格です。
この資格を取得すると、レセプトと呼ばれる患者が受けた診療について医療機関が保険者に請求する医療報酬の明細書の作成、診療報酬請求事務を行う医療事務に従事しやすくなり、医療保険事務技能者、診療報酬請求事務従事者、医療事務員、医療保険事務員と呼ばれる仕事につくことができます。
医療事務の現状
基本的に医療事務には資格は必要としません。
それなりの専門知識を必要とする仕事なのですが、資格を必要とする仕事ではなく、むしろ経験者のほうが優遇されます。
ですがそれ以外のかた、特に新卒のかたとなると採用されることは少なく、病院関係=安定した職場ですので、空きも少ないといった現状があります。
人の手が足りないような過疎地であるのならば、無資格で経験も医療事務の仕事もあるかと思いますが、それ以外の土地であれば、経験者が優遇され、経験のないかたばかりや新人の募集であるのならば有資格者が優遇されます。
これはこの仕事が医療という特殊な専門知識を理解し、来院する患者数をさばくスピードも必要になってくるためです。
診察が終わったにも関わらず、支払の段階で待たされる、もしくは待っている人が多く待合所に人が溢れているという状況を目にしたことがあると思います。
OA化が進み、経験者が行ったとしてもあの状況なのです。実務経験者が優遇される理由は、ここにあるのです。
ただでさえ、時間が掛かる事務処理であり、経験者でもそれなりの時間が掛かります。
無経験者であっても知識を習得している有資格者であれば、仕事をこなすことができます。
ですが無資格・無経験者ならば、時間が掛かることは当然といえるのです。
そうなると病院側としては、当初は戦力としては役に立ちません。
人が集まらない過疎地ならともかく、求人募集をかけている病院は仕事ができる人を求めているのです。
就職難はまだ続いていますので、無経験・無資格者の人は、この仕事につくことは特殊なケースを除いては難しいのが現状です。
そのため資格がいる仕事ではありませんが、無経験者のかたは、専門知識を得るためにも資格の取得をお勧めします。
医療保険士になるには
医療系の大学や短大、専門学校などから就職する人もいますが、保健医療士は民間の資格ですのでこの場合は、専門知識を学んでいると見込まれて就職できているのであり、保健医療士の資格をもっているのではありません。
この場合は、知識をもった新卒での採用と考えているようです。
保健医療士の資格は、通信講座で取得は可能です。
専門の学校に通う場合は、かなりの費用と時間が掛かります。
それに比べると通信講座は安価であり、時間も掛かりませんので、再就職などで保健医療士を目指すかたは、こちらのほうが取得し易いといえるでしょう。