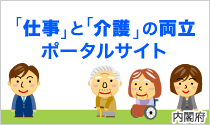コミュニケーションと摂食のリハビリ
日常的に行われているコミュニケーションは言葉によるもので、話すことや聞くことで行われており、表現をすることや食事をすることも生活の中では当たり前となっています。
しかし病気や事故、発達障害などで、話しをすることや聞くことに不自由を感じ困っている方もいます。
言語聴覚士の仕事は、言語や聴覚や食事に障害を持つ方のリハビリを行う仕事です。
脳卒中や脳梗塞による病気や事故の後遺症で起こる言語障害や聴覚障害、喉頭ガンにより声が出にくい音声障害や聴覚障害、食事を口にしてもムセてしまい、上手く噛めないことや飲み込むことができない嚥下障害にたいしての対処法のために障害のメカニズムや本質を見出しそれに則したリハビリなどの援助を行うスペシャリストです。
活躍の場所
子供から高齢者までさまざまな患者さんと向き合い、その患者さんの抱える言語障害などのリハビリを行う言語聴覚士は、医療機関の他の専門職と連携しその活動をしています。
また、医療以外の教育機関や保健や福祉の広い分野でも必要とされる人材なのです。
症状に適したリハビリを行うためには他の身体的なリハビリの専門の情報収集も行い患者さんの援助にあたることも求められます。
単独での仕事ではなく、大学病院や総合病院のリハビリ施設に就いて複数の医療関係者のチーム医療として活動することが多いです。
必要な資格
Speech Language Hearing Therapistの略称としてSTと呼ばれる言語聴覚士になるためには国家資格が必要となります。
受験資格にはSTの養成校での技能取得と卒業が必要となり、最短で受験資格を得るには高校卒業後、国が定める専門学校での履修し卒業をすることです。
STの養成課程がない大学卒の場合は指定の養成所での2年以上の学習で受験資格を得られます。
毎年1回のみ行われるSTの国家試験は専門性が高くやりがいのあるものです。
言語聴覚士の適性と就職
STの仕事では患者さんの症状に合わせてリハビリを行うというものが大きいです。
従って、豊富な知識量の他に患者さんと接するためのコミュニケーション能力も必要とされます。
また患者さんの状態を把握するための優れた観察力や患者さんへの助言が伝わりやすくするための努力や思いやりなども大切です。
リハビリテーションはすぐに成果が出る訳ではなく長期的な訓練となるために忍耐力や根気が要ります。
障害の原因の解明にたいしてじっくりと解決策を考える粘り強さが重要となります。
患者さんと実際に関わってみてその成果が見え始めた時や患者さんの喜びに近く触れることができる仕事のために充実感も高いと言えるでしょう。
STの数はまだまだ少なく手が足らないといった部分もあるので就職に困ることはありません。
また高齢化が進む社会の中でその需要は今後もますます増えていくと考えられています。