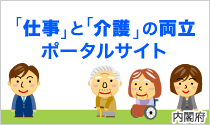体調管理をしっかり
 介護をしていると食事介助ももちろん日々1日に3回あるわけですが、食事介助の際の注意点をまずは紹介したいと思います。食事介助をする際に気をつけたい点は、テーブルとイスの高さがあっているのか、足は地面についているか、利用者の口の中の確認をできる場所で介助できるか、それをまずは確かめた上で食事介助を始めましょう。
介護をしていると食事介助ももちろん日々1日に3回あるわけですが、食事介助の際の注意点をまずは紹介したいと思います。食事介助をする際に気をつけたい点は、テーブルとイスの高さがあっているのか、足は地面についているか、利用者の口の中の確認をできる場所で介助できるか、それをまずは確かめた上で食事介助を始めましょう。
その日の水分量や食事の量、体調などは介護する人が必ず確かめてあげてください。人によっては自分で体調が優れないことを伝えることができない人もいるはずです。そして一口あたりの食事の量は多くないか、少なくないかも考えて口に運ばなくてはいけません。
使っている食器が介護を受ける人に合っているのか、少しでも自立して自分で食事をすることができる工夫をしているかも考える必要があります。食事をすべて介助すれば、言い方は悪いかもしれませんが早く片付くでしょう。
しかしやはり自分の意思で、自力で食べることができる可能性が少しでも残っているのであれば、その可能性を残してあげたいですし、自立できる方向に持っていってあげたいですね。ですから少々時間がかかったとしても、自立できる部分があるのなら、その部分は尊重してあげるべきです。
・介護食の工夫
食事介助は、ただ食事を食べさせてあげればいいだけではありません。間違った食事介助をしていると介護を受けている人が亡くなることもあります。例えば姿勢が悪いのに、そのまま食べさせていると誤嚥の原因になりとても危険です。
食べさせ方の注意
地面に足がついてないとバランスが取れなくて食べづらいこともありますし、食べている最中に事故を起こすこともあります。必ず口の中は確認しながら食事介助はしなければいけません。場合によって入れ歯が外れて飲み込んでしまうことなどもあるので、毎回確認が必要です。
一口の量が多すぎても少なすぎてもよくないのは、介護されている人が食べた気がしないこともあるからです。ですから適当な量をその人のペースで口の中に運んで上げなければいけません。食事介助は、1日に3回ありますし、そのつどその人の状態によってはすべてを口の中に運んで入れてあげなければいけませんから、時間もかかることと思います。
しかし、食事は人間の三大欲求の1つでもありますので、介護が必要な体になっても食べるという楽しみを忘れてもらわないためにも工夫をして介助していきたいですね。そのために歯それぞれに合う形状の介護食の用意も必要になってきます。