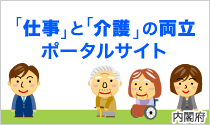体を清潔に保つ
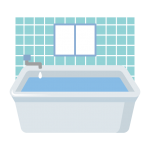 介護の入浴介助は介護してもらう人も介護をする人にとっても大仕事といえるかもしれません。専門の知識を少し身につけておくだけでも入浴介助がスムーズにできるようになりますし安全に入浴介助ができるようになります。入浴、それは何の目的で行うのかといえば体の清潔を保つことが目的です。
介護の入浴介助は介護してもらう人も介護をする人にとっても大仕事といえるかもしれません。専門の知識を少し身につけておくだけでも入浴介助がスムーズにできるようになりますし安全に入浴介助ができるようになります。入浴、それは何の目的で行うのかといえば体の清潔を保つことが目的です。
そして全身の血液の流れを浴して、硬くなった関節も入浴することによって柔らかくなります。そして全身のリラックス効果もありますし、全身の状態をチェックする役目もありますので、皮膚の疾患になっていないか、床ずれができていないかの確認をするためにも介護では重要な役目を果たしています。
ですが入浴は血圧が変化し、体にかなり負担を与えることにもなります。お風呂に入る前には必ず体の状態や体調、入浴後にも体調の変化には気を配らなければいけません。
入浴前は排泄をしておく、血圧、体温、脈拍が正常であることを確認して、食事の1時間前後には行わないこと、脱衣所や浴室が寒いと急激な体温変化で急変することもありますので、温度は22度から25度に設定しておきます。
・事故防止について
転倒したり滑ったりしないように配慮して、心臓より下まで湯船につかることで心臓への負担を減らしましょう。そしてお風呂に入ってからも気分が悪くなっていないか、湯冷めしないようにしっかりと拭いて乾燥も徹底してあげましょう。水分補給はこまめに行い脱水を予防する必要もあります。
入浴介助の手順
入浴介助の手順ですが、介護を受ける人の度合いによってもどこまで手伝うのかは違ってくると思いますが、ほとんど自立して入れる人でも介助と見守りは必要です。
すべて介助しなければ入れない場合には、イスに座れるなら浴槽にイスを置いて体を洗ってあげるといいでしょう。体を洗う順番は上半身から下半身、陰部の順番です。そして自分でできることが少しでもあるのなら、自立を促すために自分でできるところは自分でやってもらうといいでしょう。
入浴は本当に大変でヘルパーさんや訪問入浴に依頼しているという人も多いかと思います。しかし介護度の度合いによっては自分たちで入れなければいけないこともありますので、その際は事故につながらないように配慮しながらあわてずに入浴介助をしていきましょう。
別枠で入浴介助での事故防止のポイントについてまとめていますのでそちらも参考にして、入浴時に事故を起こさないように環境を整えたり、介助の仕方を工夫したりしていきましょう。